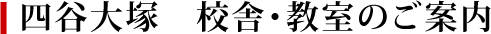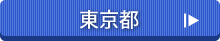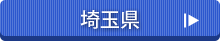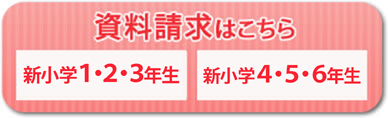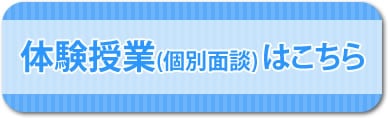四谷大塚 校舎のご案内

上大岡校舎 和田です。
<今週の学習について>
6年は合不合おつかれさまでした。算数の大問6,7,8は解説授業がしたくてしょうがない。美しい解答を自慢し合いたいですね。解答よりよくね?ってのがあったら送ってきてください。今晩あたり他教科を解く予定です。
5年は差集め算に苦しんでいる頃では。全体の量÷1コ当たりの量=個数というのを差で捉えるのが大切。The 算数なのでわたしは好きな単元です。数学の登竜門として、等式をつくって解ききるのもアリ。これも本当は解説したいよね。予習ナビは四谷大塚でもすばらしい先生が解説しているので、是非隅々見てみましょう。
4年は図形。しかも面積。一番好きな単元です。魅せ方一つでおもしろさが変わります。
プリントは解いてるかな?面積がわかれば、わだからの挑戦状もとけるはず。
1~3年は永泉先生からの挑戦状は解いてますか?『解答来てるかな~』と先生が楽しみにまってますよ!
さて、今日はわたしが好きな言葉を一緒に考えてもらおうと思います。
『愚者は経験に学び、賢者は歴史より学ぶ』
ドイツ初代首相のオットー・フォン・ビスマルクの言葉を意訳したものです。
直訳すると、
【愚者だけが自分の経験から学ぶと信じている。私はむしろ、最初から自分の誤りを避けるため、他人の経験から学ぶのを好む。】だそうです。
よく誤解されやすい名言として取り上げられています。事実がどうというよりは、この言葉のもつ意味を捉えて欲しいです。
経験とは?自分の過去
歴史とは?他人の過去です。
大人はさまざまな経験をしています。
だから『勉強しなさい!』という思いを、ついこどもに言いたくなります。
一方こどもたちは、圧倒的に経験も歴史も不足しています。
知らないのだから、よくわからないのです。与えられた言葉が【事実】か【意見】かの区別がつきません。
ここで私の伝えたいことは、自分から歴史を学びに行こうよ。ということです。
小学生のときの、わたしと父親との出来事(歴史)です。
原因は忘れましたが、父親に『けんかうってるのか?』と言われて
わたしは『いくら?』と答えました。
ボコボコにされたことを覚えています笑
あ、真似しないでね。歴史(わだの失敗)から学んでね。
歴史を学ぶことは、他人の人生を自分の価値観や生きる知恵に変えられるということです。温故知新。
これから新しい問題がでてきたときに
1人の人生 VS 100人の人生から得た知恵 で考えたら
そりゃ100人の人生から学んだ価値観の方が色々な見え方をするし、より正解に近い考え方をもつよね。ってことです。
じゃあどうすれば歴史を学べるんだ!というと
ずばり、本ですね。
本にはその人が生きてきた価値観が詰まってます。
不思議なもので、同じ本を読んでも人によって感想や気に入った文章がちがいます。
もっというと、10年前に読んだときに気になる文章が違ったりします。
だから、自分が今気に入っている本を同じようにおもしろい!って言う人をみつけるととてもうれしくなります。そういう経験ありませんか?
いろんな歴史を学び、それを自分の経験とすることができる人が
きっと将来の問題を解決できるのではないでしょうか。
大人のいう『勉強しなさい』ってこういうことです。たぶん。
今当たり前とされている考え方や定理は、何年もかけて誰かが考えてくれました。
算数のピタゴラスの定理(三平方)とか理科の万有引力の法則とか。
国語の文章問題、社会での法律や制度、伝記なんてまさにそう。
そう考えてみたら、つまんないなーと勉強するより、なんでそうなったの?深く調べてみましょう。それだけの時間が、今みなさんにはあります。
今当たり前じゃないことは、もしかしたら100年後の当たり前かもしれませんよ。
ゴッホの絵が死後評価されたように。ガリレオの地動説が最初は受け入れてもらえなかったように。
後世に自分を残せたら、かっこいいですよね。
わだ
<おもしろい質問の共有>
4年生より
Q.台風の番号はなんの順番ですか?
→A.気になった方は調べてみましょう!
結構世の中謎だらけ。なぜ?と問いかけてみよう。